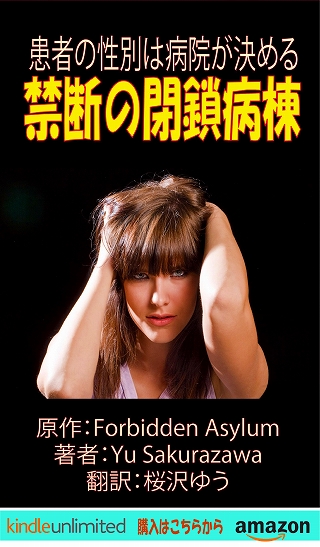
禁断の閉鎖病棟
患者の性別は病院が決める
【内容紹介】監禁・緊縛により強制女性化させられるホラー系のTS小説。主人公レイの運転する車が辺鄙な場所で故障し、スマホのバッテリーが切れており電話を借りようと人家を探す。古い病院に辿り着き電話機のある部屋に案内されるが、事務長と看護師はレイが男性であるという妄想に憑りつかれた女性だと決めつける。
原題:Forbidden Asylum
原作者:Yulia Yu. Sakurazawa
翻訳者:桜沢ゆう
「閉鎖病棟」とは精神科病院の病棟で出入り口が常時施錠され入院患者や面会者が自由に出入りできない病棟を示す言葉で、開放病棟の対語である。
第一章 狂気の事務長
私は夢見心地で高速道路を運転していた。私の愛車、マルチ・スズキのアルト800を運転するのはこの上ない喜びだ。初めて買った車だから愛着があるというだけでなく、マニュアル・シフト車のハンドルを握り、最高のタイミングでクラッチを踏んでギアをシフトして他の車をビューンと追い抜くのは快感としか表現のしようがない。セルリアン・ブルーのアルトは私の感性に呼応して思い通りに動いてくれる。父の遺産を引き継いでいたので、その気になればBMWの5シリーズでもトヨタのSUVでも買えたが、欲しかったのはこのアルトだけだった。
カルナタカ州の旧国道4号、通称NH4は映画の題になったこともある趣のある国道だ。郊外に出ると窓の外の景色は退屈な田舎の風景でしかない。まだ朝なのに荒地を走るタールとコンクリートの道路を強い日差しが焼き焦がす。樹木はまばらで五十メートルに一本立っていればまだ良い方だ。でも、大都市バンガロールの気違いじみた喧噪と交通渋滞を逃れ、遠く離れた田舎を一人でぶっ飛ばす気分は格別だ。
気持ちよくトップギアで走っていたが、突然車がガクガクっとなった。アクセルを踏んでも反応しなくなり、緊急停止を試みたがブレーキもきかない。必死でハンドルにしがみ付き、何とか路肩に停車して、ほっと胸を撫で下ろした。
ボンネットを開けたが、特に煙や蒸気が噴出しているわけではなく、エンジンオイルをチェックしたところ正常範囲内だった。私は特にメカ音痴ではないが、何をしたらよいか分らず、お手上げだった。子供の時から住み込みの運転手兼メカニックが居る家に育ったので、自動車が故障した場合の対応を学ぶ機会はなかった。
意識しないうちにNH4から分岐する道に入っていたようで、そこは人っ子一人見当たらない荒れ果てた場所だった。車が通れば近くのカーショップまで乗せてもらえるのだが、停車してから十分間、一台の車も通らなかった。
仕方ない。家からはちょっと遠いがディンプルに電話して迎えを頼むことにしよう。ディンプルとは妻の愛称だ。彫りの深い顔に浮かぶ可愛いえくぼ……。私が困っていたらいつも助けに駆け付けてくれる、世界一頼りになる相棒だ。非常にしっかりしていて、家の中では頭が上がらないが、ディンプルの優しい笑顔を思い出すだけで気持ちが和む。
助手席に置いたバッグからスマホを取り出す。
――あっ、電池が切れてる! 警告が出ていたからUSBプラグを挿し込もうと思っていたのに、つい忘れていた。困ったぞ……。
まずいことにバッグには小銭入れしか入っていなかった。
車のキーを回すとメーターのランプが点灯したので、停車したままでスマホを充電することは多分可能だろう。後から思うと、そうしていればよかったのだが、二十五歳の未熟な私は何もせずに待つことには耐えられず、小銭入れをポケットに入れて車を降り、人気がありそうな方向へと歩き出した。
イバラが生い茂った田舎道をトボトボと歩く。
暑い! 日差しが高くなってとにかく暑かった。一キロ近く歩くと、ヒンヤリとした風が流れて来た。近くに川が流れているのだろうか。そのまま歩いていると大きな菩提樹が見えてきた。そして、その菩提樹の向こうに建物が忽然と姿を現した。こんもりとした木に隠れて見えなかった建物が視界に入ったというだけの話なのだが、その時の私にとっては感動の光景だった。
私は子供のようにはしゃいで駆け出した。菩提樹に近づくと背後の建物がはっきりと見えてきた。
それは外壁を白で塗装された建物で、清潔な感じがした。一般の住宅よりはずっと大きいが、大きなビルというほどではない。取り立てて特徴の無い普通の建築物であり、バンガロールには同じ形の建物が何百何千とあるだろう。「取り立てて特徴が無い」という言葉が、この建物を表すには最も適切だと思った。
何の建物かというと小さな工場、小さな役所または診療所というあたりではないだろうか。鉄でできた背の高い門に近づくと「ヴィンセント病院」という看板が目に入った。私の三つ目の推測が当たっていたわけだ。
一見したところ、ヴィンセント病院について特に不審な感じはしなかったが、ただ「高圧注意! 壁には高圧電流が流れています」という標識が目についた。どうして病院の壁に電気を流すのか意味不明だ。これは人間用の病院ではなく、猛獣を収容するアニマル・ホスピタルなのだろうか? それとも、最近産婦人科病院からの誘拐事件が相次いだ結果、門以外からの人の出入りを完全に遮断するという対策を講じたのだろうか……。
ところが、近づいてみると意外にも門番や警備員は居らず、鉄格子でできた門のラッチ式の鍵を手で開けると難なく中に入ることが出来た。前庭には鉢植えが幾つか置かれており、建物の玄関ドアへとつながっていた。ドアを開けて中に入るとフロントロビーがあり、受付窓の向こうに事務所が見えた。
私は受付窓からオフィスの中を覗き込んだ。男が一人事務机に座っていた。四十代半ばぐらいだろうか。客観的に見て普通の男性だった。顔立ちはよく、白髪交じりの髪は少し縮れているが、年の割に引き締まった体型をしていた。ただ、安っぽいポリエステルのカッターシャツ、首にかけた味気の無い金メッキのチェーン、そして何よりもシャツの上から透けて見える胸毛の気持ち悪さに、ついイライラしてしまった。
しかし、そんなことはどうでもよかった。大事なことはこの男性に助けを求めることだった。
「あのう、すみません」
「はい、なんですか?」
「病院の方ですよね?」
「事務長のアショックですが」
抑揚が無くて何の特徴も無い声で返事があった。この建物の外観と共通点を感じた。
「私はレイと申します。バンガロールからNH4を走っているうちに側道に入ったみたいなんですが、車が急に故障して動かなくなってしまいました。スマホも電池が切れてしまったので、ここまで十五分ほど歩いて辿り着きました。家内に迎えに来てくれという電話をしたいので、携帯電話を使わせていただけないでしょうか?」
「それは災難でしたね。残念ながら私は携帯電話を持っていません。この病院のスタッフも誰も持っていません。この病院は……何と言うか、精神を病んでいる人のための病院なので、余計な精神的負担をかけないよう、建物の中への携帯電話やスマホの持ち込みは禁止しているんですよ」
「でも、そのパソコンはネットにつながっていますよね? そこから妻にメールを送信させていただけませんか? メールだと電話と違ってすぐには通じないかもしれませんが……」
「レイさん、恐縮ですがパソコンはネットにはつながっていませんし、WIFIもありません。もし患者が夜中に事務所に忍び込んでメールを送信したりブラウジングしたら困りますんでね。うちの患者さんは処置するために入院しているのであって、楽しむためにここに居るわけじゃありませんから」
「分かりました、アショックさん、他を当たってみます。スマホがそろそろ充電されているはずなので車まで歩いて戻る方が早いかもしれません」
それまでぶっきらぼうだった事務長の物腰が急に柔らかくなった。
「ちょっとお待ちください。この炎天下を十五分も歩いて熱射病になったら、それこそ大変です。緊急通話用に固定電話を一回線だけ引いてあって、その電話機が三階にあります。お使いになりますか?」
「助かります! 是非お願いします」
「じゃあ三階までご案内しましょう」
アショックについて古風なベンガラ塗りの階段を三階まで上った。一応ちゃんとした病院のようなのにエレベーターが無いとは驚きだった。階段の途中で、だらしない服装の年配の男が階段のさび付いた手すりにしがみついているのを見かけた。
私がその男の横を通過した時、男は濃い茶色のフレームの眼鏡に右手をかけて私をにらんだ。
「ついに宇宙がその姿を現した。わしの家のジャグジーの中に宇宙があるんだ!」
急に男が叫んだので心臓が飛び出しそうになった。アショックは私の肩に手を置いて言った。
「心配ご無用、あの男は妄想しているだけです。シバという名前で、ただの貧乏人ですが壮大な幻想を抱いていて、自分のことを画期的な発見をした偉大な天体物理学者だと思い込んでいるんです」
「そうですか……」
アショックが患者の病状を説明するのに嘲るような口調で話したことに嫌悪感を覚えた。
心の病というものは簡単にコントロールできるものではなく、心の病を持つ人を嘲笑するのは全く非倫理的だ。アショックの無神経さにムカムカと腹が立ってきたが、電話機があるはずの三階の部屋にやっと到着して我に返った。
部屋に入って気づいた最初のことは、壁面の約二メートルの高さに長方形の金属扉があるということだった。スイッチボックスの扉にしては大げさな感じだった。
それはガラス窓と造り付けの小机だけがある小部屋で椅子もない。机の上には黒い電話機が置かれていた。それは子供の時に家にあったのと同じ回転ダイヤル式の電話機で、一九九〇年代にタイムスリップしたような気持になった。
――奇妙だ。
不思議な感覚だった。ヴィンセント病院には時間が流れているのだろうか……。
震える指で妻の携帯電話の番号をひとつずつダイヤルした。アショックは小部屋から出て行ってドアを閉めた。アショックがプライバシーを気遣ってくれたことには意外な気がした。ダイアルし終えて応答があるまでの時間が長く感じられた。ディンプルの少しハスキーで魅力的な声が聞えた時、私は救われた気持ちになった。
「もしもし、どなたですか?」
「僕だよ、レイだよ!」
「あなたなのね? どこから電話してるの?」
私は今日の苦労の一部始終を妻にぶちまけた。ディンプルは私たちの親友のサンジャイと一緒にショッピングモールにいるようだった。
「ヴィンセント病院はNH4から分岐した道路の近くにあるはずだよ。正確な場所はネットで調べてみて。大きな菩提樹が目印だ。出来るだけ早く来てね!」
「パニックにならないで! NH4ならよく分かっているから簡単にたどり着けると思うわ」
「NH4からどこでどう側道に入ったのか、自分でも分からないんだけど、分岐してからかなり走ったみたいなんだ。殆ど人気のない場所に来ちゃったから」
「悪い子ね、一人でそんなに遠くまで行くなんて」
ディンプルは子供に説教するような口調で私に言った。
「サンジャイと私がそこにたどり着くまでには、多分一時間半ぐらいかかりそうね。交通渋滞がひどければ二時間かかるかも」
「ごめんね……」
「まあ、いいわよ。ええと、病院の名前をもう一度言って」
「ヴィンセントだよ。ヴィンセント病院」
「ヴィンセント病院? 聞かない名前ね。ねえ、サンジャイ、ヴィンセント病院って知ってる?」
サンジャイの声は受話器には聞こえなかったが、ヴィンセント病院という名前は知らないようだ。
「すぐに出発するから心配しないで待っていて。途中で知り合いのメカニックを拾って行くとサンジャイが言ってる」
「本当にごめんね。二人に迷惑をかけて」
と言って電話を切った。
ディンプルの優しい声を聞けただけで幸せだった。妻と私の二人だけなら途方に暮れていたかもしれないが、サンジャイが居るから何とかしてくれる。本当に頼りになる最高の男だ。
妻に電話で助けを求めるという最重要課題を終えてひと息ついた。後はロビーまで下りて行って妻とサンジャイの到着を待つだけだ。知り合いのメカニックを拾ってくると言っていたから、きっと愛車のアルトに乗って家に帰れるだろう。
小部屋のドアを開けるとアショックが心配そうな表情で立っていた。
「お友達に電話は通じたかい、レイチェル?」
――はあ? レイチェルだって?
アショックは今私をレイチェルと呼んだ。若々しく、男らしくてスポーティーなこの私を、女の名前で呼ぶとはどういうつもりだろうか? 私はスリムだが身長もあり、女性を連想させるところはひとつもない。
不愉快だと一瞬思ったが、真面目な顔をして性別絡みの冗談を突然言い出したアショックを見ていると、可笑しさが急にこみ上げてきた。
「アハハハ。事務長さんって、相当パンチのあるユーモア・センスがあるんですね!」
アショックは笑わなかった。それどころか、真剣で打ち沈んだ感じの心配顔になった。アショックの表情を見ていると、私が一人で笑うわけにはいかないという気がした。
気まずい沈黙の後でアショックが口を開いた。
「レイチェル、薬は時間通りにちゃんと飲んだのか?」
続きを読みたい方はこちらをクリック!





